2024年1月から開始となった「新NISA」では対象外となっている、毎月分配型投資信託を高齢者向けの販売を政府が検討を始めている。はたして、「プラチナNISA」は、「貯蓄から投資」に流れをさらに勢いづけることはできるでしょうか。
この「プラチナNISA」とは、いったいどんなようなものか、詳しく解説します。
プラチナNISAとは
「プラチナNISA」は、日本において65歳以上の高齢者を対象に、2026年の開始が検討されている新たな非課税投資制度です 。この制度の大きな特徴の一つとして、現行のNISA制度では原則として対象外とされている毎月分配型の投資信託が組み込まれる可能性が挙げられます 。
この構想は金融庁によって検討されており、「資産運用立国」をめざす岸田前首相が会長をつとめる、自民党の資産運用立国議員連盟からも提案されています。
その背景には、日本の個人金融資産の多くを高齢者が保有している現状があり、これらの資金を投資に誘導することで経済の活性化を図る狙いがあります 。
つまり、現在の「新NISA」では購入することができない毎月分配型商品を、65歳以上の高齢者限定で「プラチナNISA」として販売していこうというものである。
高齢者限定するのはなぜですか?

日本では家計の金融資産総額の6割にあたる約2100兆円のうち1300兆円を60歳以上の高齢者が持っているといわれています。このお金を投資に回すことで経済を活性化させ、高齢者自身の収入増加にも繋げたいと政府は考えています。その切り札となりそうなのが、「毎月分配型」の投資信託です。
また、60代、70代の約8割は、これまで金融知識に関する学ぶ機会も少なく、「損をしたくないから投資しない」「投資はギャンブルである」という損失回避傾向が強いため、「毎月分配型」の投資信託で「貯蓄から投資」につなげようというのが政府の目論見です。
現行の「新NISA」は、長期的な積立投資を前提としており、長期資産運用には適していないとされる毎月分配型の投資信託を原則として対象外としております。
しかし、高齢者は、若い世代とは異なり、長期的な資産成長よりも、むしろ安定した収入や資産の維持に関心があることが多いと考えられます 。また、投資期間も若年層に比べて短くなる可能性があり、すぐに収入を得たいと考える高齢者にも、この毎月分配型の投資信託をNISA制度に導入することで、積極的に非課税投資を促そうとするのが理由です。
つまり、現行NISAが長期的な資産形成を重視しているのに対し、プラチナNISAは資産の活用、つまり取り崩しながら生活に役立てることを想定している点が大きな違いと言えます 。
プラチナNISAの上限額(予定)は
プラチナNISAの非課税投資枠の上限額は、2025年4月時点ではまだ決定されていませんが、新NISAの生涯投資枠1,800万円とは別枠で設けられる可能性が高いと見られています 。
ある情報では、年間100万~120万円、5年間で最大600万円という非課税投資枠が設定されるのではと言われております。
また、新NISAでは特に年齢の上限はないため、既存のNISA口座で保有する対象資産をプラチナNISA口座へ移行(スイッチング)できる可能性も議論されています 。しかし、一方では、プラチナNISAは現行のNISAや積立NISAと併用できないと明記されており、今後の公式な発表を注視する必要があります。
プラチナNISAのメリット

プラチナNISAの最大のメリットの一つは、毎月分配型の投資信託を通じて、安定した月々の収入を得ることが可能となり、公的年金以外の定期的な収入として退職後の資金計画が立てやすくなるという利点があります 。
また、NISAの特徴である運用益が非課税になることで、手取りの額が増え、効率的に資産を活用することができます。
プラチナNISAは、退職後の高齢者が公的年金の収入だけでは老後の生活資金が不足する可能性がある中で、保有する貯蓄を有効に活用して、安定的な収入を得るための手段となりえます 。
つまり、高齢者が保有する資産を、非課税制度を使って上手に活用し、「運用」しながら取り崩すことで老後の経済的に安定した生活に役立てることを想定しています。
確かに、毎月分配型の投資信託は長期運用には適していないが、比較的運用期間の短い高齢者にとっては、「運用」して資産を増やすながら分配金を得ることができるながら取り崩すことで資産寿命を延ばすことができる「資産形成」世代を過ぎた、60歳以上の「資産運用(管理)」世代にとっては良い金融商品と言えるでしょう。
プラチナNISAのデメリット

プラチナNISAの検討対象となっている毎月分配型の投資信託には、3つのデメリットが考えられます。一つ目が、いわゆる「タコ足配当」(元本取り崩し)のリスクです 。これは、毎月支払われる分配金が、運用状況によっては必ずしも投資信託の運用益から支払われるとは限らず、元本を取り崩して支払われることがあります。
投資家は高い分配金に魅力を感じるかもしれませんが、それが単なる元本の払い戻しである場合、長期的に見ると資産を減少させてしまう可能性があります 。
二つ目は、毎月分配型の投資信託は、一般的な投資信託に比べて手数料が高く設定されている場合があります 。毎月分配を行うための事務コストなどがかかるため、信託報酬が高めに設定されている商品も少なくありません 。
プラチナNISAで取り扱われる可能性のある毎月分配型ファンドは手数料・管理料が高い傾向にあるとも言われております。
三つめは、毎月分配金を受け取ることで、複利効果が働きづらくなるというデメリットもあります。
長期的な資産形成を目指す場合には、収益を再投資することによる複利効果が大きくなりますが、毎月分配型では、分配金を受け取ってしまうと、その分が再投資されず、複利効果が働きにくくなります。
「新NISA」から外された「毎月分配型」とは
現在、新NISAでは、毎月分配型の投資信託は対象外となっています。なぜなら、上述のとおり、「毎月分配型」の投資信託は、一定額の分配金を毎月定期的受け取ることで、運用益が再投資されずに複利効果が得にくいため、長期で資産を増やしていくという「新NISA」の主旨に沿わないため対象商品から外されています。
さらに、毎月分配型の投資信託は、運用状況が良くない場合、投資家の元金が取りくずされて目減りしていく可能性があります。そうしたリスク説明が不十分だと、投資したお金が目減りしているとは思っていない投資家から苦情が殺到する可能性が大いにあります。
実は、この状況が17年前にも起こっておりました。
売れすぎた!グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)とは

毎月分配型投信の代表といえば、いわゆる「グロソブ」と呼ばれている商品です。
国際投信投資顧問の「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)」は、2008年には純資産総額5兆7000億円を超える超巨艦ファンドに成長しました。
ちなみに、現在(2024年10月)人気のある投資信託商品として、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)がありますが、その純資産総額は、5兆7696億円でとなっていますので、ほぼ同規模の純資産総額でした。
「グローバル」とは「世界中の」ということ、「ソブリン」とは「主権国の」ということを意味します。一般的に先進諸国の国債は優良格付債と認識されています。毎月分配型投信のメリットは、毎月分配金が受け取れることです。グローバル・ソブリン・オープンの場合、2014年1月から毎月20円で推移しています。これは1万口あたりの税引前の金額です。設定来の分配金累計で計算すると、約4.6%の年利回りとなります。
1000万円の投資信託を買うと、毎月必ず4万円の分配金が得られるということで、証券会社も「元本割れにならない確実な債券で運用し、そこから出た利益が年金の足しになるので将来も安心」という殺し文句で、高齢者に大々的に販売しました。
主要先進国の政府および政府機関が発行している元本保証の安全な国債を主な投資対象としているので、安全、確実で破綻の心配もなく、そこで得られた利益は配当として分配されるので、毎月、安定した収入が確保できるというのが売り文句でした。
買った人たちの多くは、投資初心者。「眠っているお金で投資するだけで毎月もらえる年金が増え、老後は安心です」という言葉を、そのまま鵜呑みにして、なけなしの老後資金を銀行から引き出し、金融機関に持ち込みました。
しかし、ピーク時には純資産総額が5兆円超もあったグローバル・ソブリン・オープンも、今では約2,800億円ほどに減ってしまいまい、ファンドそのものの存続が危ぶまれる状況になっています。
また、1000万円に対して月4万円だった分配金も徐々に下がり、2020年からは月5000円に激減しています。しかも、投資した1000万円も徐々に減っていき、2025年4月18日現在では508万円と約半分になっています。
これは、投資信託に組み込まれている債券は安全性を重視したものなので、その後の世界的な低金利の中では利回り4%以上というのは非常に困難な運用状況に陥り、さらに利回りはどんどん低下していきました。
また、為替ヘッジもついていないので、発売当初は1ドル=約150円の為替が2011年には1ドル=80円の円高となったため、毎月定額の分配金を必ず投資家に支払わなくてはならないために、結果的に元金の取崩しが継続的に発生したためであります。
参考記事:仕組みを知ろう!: 毎月分配型投資信託とは

まとめ

「プラチナNISA」は、65歳以上の高齢者向けに提案された、毎月分配型投資信託を中心とした非課税投資制度です。定年後の年金収入を補填するための定期的な収入源となり、投資益や分配金が非課税となる点は大きなメリットです。
一方で、毎月分配型投資信託には、元本取り崩し(タコ足配当)のリスクや、手数料が高い可能性があるという重要なデメリットも存在します。また、定期的な分配金を受け取ることで、長期的な複利効果が得られにくくなる可能性もあります。
しかし、最も危惧するのは、金融機関等の販売会社が「この金融商品は、新NISA同様、金融庁のお墨付きプラチナ商品です。」とこれまで金融知識を学ぶ機会の少なかった高齢者をターゲットに販売攻勢をかけることが安易に想定されます。
また、上述のとおり、高齢者にとって「毎月分配型」の仕組みは良い金融商品と言えますが、金融機関からのリスク等の不十分な説明によって、高齢者が提供される金融商品のリスクを十分に理解せずに購入してしまう恐れがあります。
そうならないように、ファイナンシャルアドバイザー等専門家に相談することを推奨します。また、制度の最終的な規制や詳細については、今後の政府発表に注目していく必要があります。
「グロソブ」にような結末にならないことを祈っております。





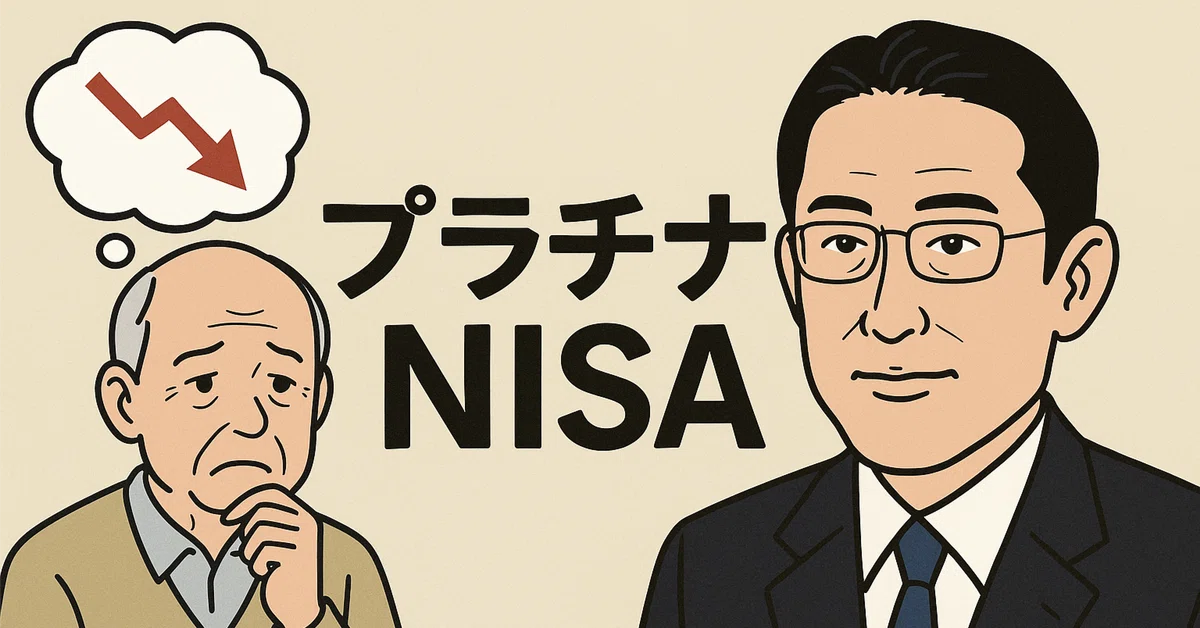


コメント