世の中で「今、これがアツい!」と話題になっているテーマに絞って投資する「テーマ型投資信託」が注目を集めています。
テレビやニュースでよく聞く言葉が投資のテーマになっているので、「これなら私でも分かりやすい」「儲かりそう!」と感じる方も多いかもしれません。
しかし、シニア世代の皆さんが大切に育てたい「長期の資産運用」という視点で見ると、実はテーマ型投資信託には注意すべき点がたくさんあります。
このブログ記事では、テーマ型投資信託について、以下の3つのポイントを分かりやすく解説します。
- テーマ型投資信託とは?(何が魅力なの?)
- テーマ型投資信託のメリット(なぜ売れるの?)
- テーマ型投資信託を長期運用で買ってはいけない5つの理由
この記事を読んで、ご自身の資産運用商品を選ぶ際の参考にしてください。
1. テーマ型投資信託とは?
テーマ型投資信託とは、簡単に言えば、世の中で「今」話題になっている特定のテーマ(流行)に絞って投資をする金融商品です。
どんなテーマがあるの?
例えば、最近よく聞く「AI(人工知能)」や「フィンテック(ITを使った金融)」、「eスポーツ(ゲームの競技)」など、時代を象徴する新しい技術やトレンドがテーマになります。
過去にも、「シェールガス」などのエネルギー関連や、「環境(ESG)」といった社会の関心事など、その時々のブームに合わせて様々なテーマ型ファンドが生まれてきました。
魅力は「分かりやすさ」
このタイプの投資信託が人気を集める一番の理由は、投資先が分かりやすいことです。
- 「AI」なら、AIを開発・利用する会社に投資する。
- 「ゲーム」なら、ゲーム関連の会社に投資する。
というように、テーマが明確なので、投資にあまり詳しくない方でも「これは知っている」「将来性がありそう」とイメージしやすいのです。販売する側にとっても、お客様に説明がしやすい「売りやすい商品」だと言えます。
2. テーマ型投資信託の3つのメリット(なぜ売れるの?)

テーマ型投資信託が売れ行き好調なのには、次のような理由があります。
メリット1:投資先がイメージしやすい
前述の通り、「AI」「DX(デジタル変革)」といったテーマは、テレビやニュースで頻繁に取り上げられるため、なじみがあり、何にお金を託すのかが理解しやすいのが大きな魅力です。
メリット2:「儲かりそう!」な期待感がある
自分の関心あるテーマと世の中の流れがピタッと合えば、短期間で大きな利益を得られる可能性があります。
「このテーマはきっと伸びる!」と感じたとき、数ある会社の中から自分で銘柄を選ぶのは大変ですが、テーマ型投信なら、その分野の会社に効率よくまとめて投資できるイメージがあります。
メリット3:市場平均より高いリターンを狙える可能性がある
通常の投資信託が幅広い会社に分散して投資する(市場全体に満遍なく投資する)のに対し、テーマ型は特定のテーマに関連する会社に集中して投資します。
この「集中投資」が成功すれば、市場全体が上がった時よりも、はるかに大きなリターンを得られる可能性があります。
3. テーマ型投資信託を長期運用で買ってはいけない5つの理由
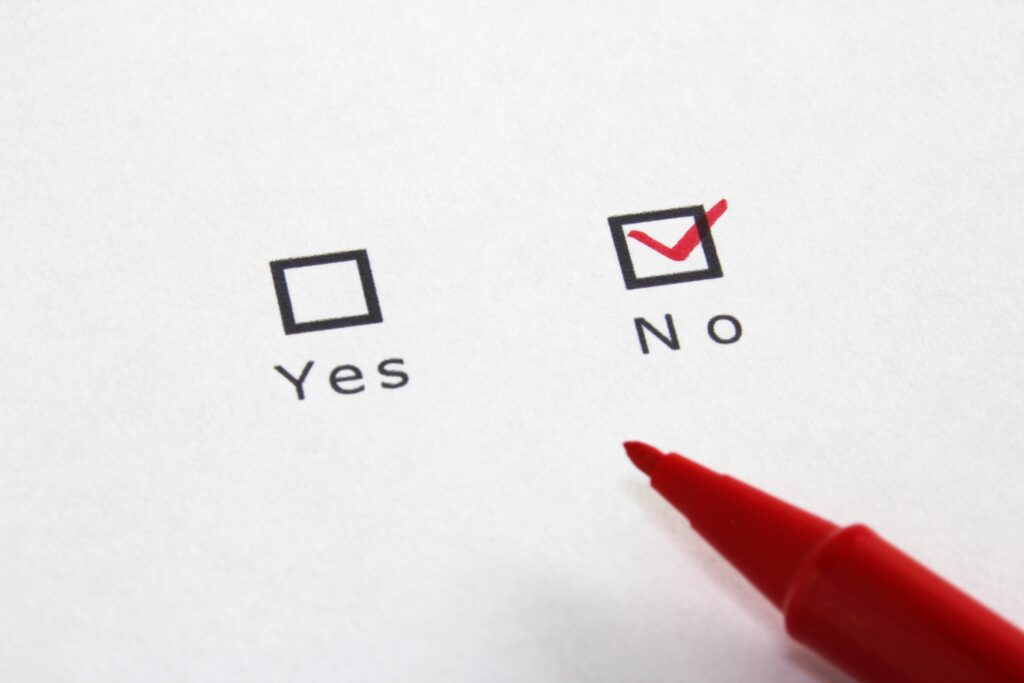
テーマ型投資信託には魅力がある反面、特にシニア世代の皆さんが目指す「コツコツと長期で資産を育てる」という目的には向かない、注意すべき点があります。
理由1:投資の基本「分散」に逆行している
投資でリスク(値動きの幅)を抑えるための基本は「分散投資」です。いろいろな資産や、たくさんの会社に分けて投資することで、もし一部が不調でも、他の好調な部分がカバーしてくれます。
ところが、テーマ型投資信託は、投資する会社や業種を特定のテーマで絞り込んでしまうため、せっかくの「分散のメリット」を自ら放棄していることになります。テーマが外れたり、そのテーマの関連企業全体が不調になったりすると、損失が大きくなるリスクが高まります。
理由2:ブームが去ると「短命」に終わりやすい
テーマ型投資信託は、「その時々の話題」に投資するものです。流行(ブーム)には必ず終わりがあり、テーマによってはあっという間に世間の関心から消えてしまいます。
実は、この種の投資信託は昔からありましたが、過去を振り返ると、その多くが短命に終わっています。テーマのブームが去ってしまうと、資金が集まらなくなり、運用が立ち行かなくなるケースが多いのです。
資産運用は、20年、30年と長く続けることで効果が大きくなります。短期間で終わってしまう可能性のあるテーマ型は、長期の積み立てには適していません。
理由3:手数料(コスト)が「高い」
テーマ型投資信託の多くは、私たちが支払う手数料が他の一般的な商品よりも高めに設定されています。
- 販売手数料(買う時にかかる費用): 2%~3%程度が多い
- 信託報酬(持っている間にかかる費用): 年率2%前後と高めが多い
たとえば、1000万円投資すると、購入時だけで20万円〜30万円、さらに毎年20万円程度がコストとして引かれる計算になります。
手数料は、確実にリターン(利益)を減らす要因になります。長期で運用する場合、このコストの高さは大きな不利になってしまいます。テーマが変わるたびに乗り換え(売買)を繰り返すと、そのたびに手数料がかかるのも痛い点です。
理由4:多くのケースで「高値づかみ」になりがち
テレビやニュースで話題になるということは、既に多くのプロの投資家がその情報に注目し、関連する会社の株価が上がってしまっている可能性が高いです。
私たちが「このテーマは良さそう!」と思って買い始めた頃には、既に株価がかなり高い水準にある、いわゆる「高値づかみ」になってしまうことが多いのです。
プロは先に動いています。一般の投資家が「分かりやすい」と感じて買い始める時には、短期的な上昇のピークに差し掛かっているかもしれない、ということを知っておきましょう。
理由5:「わかりやすい」と「儲かる」は全くの別物
テーマ型投資信託が売れる最大の理由は「わかりやすい」からです。しかし、何度もお伝えしますが、「わかりやすい」ことと「必ず儲かる」ことは全く別です。
- 「AIはブームだから、関連会社の株も上がるだろう」
- 「5Gの時代だから、きっと儲かるだろう」
というように、誰でもイメージしやすい錯覚に騙されないように注意が必要です。
「あのテーマはブームになったけど、結果的に大して儲からなかった」という投資信託もたくさんあります。「短期間で大きく稼ぎたい」という短期売買(デイトレード)が得意な投資家向けの側面が強い商品だと認識しましょう。
参考記事:【要注意!】「一攫千金」を狙う短期売買(デイトレード)の落とし穴:あなたの資産を守るために知ってほしい3つのリスク

まとめ:長期運用には「分散と低コスト」を
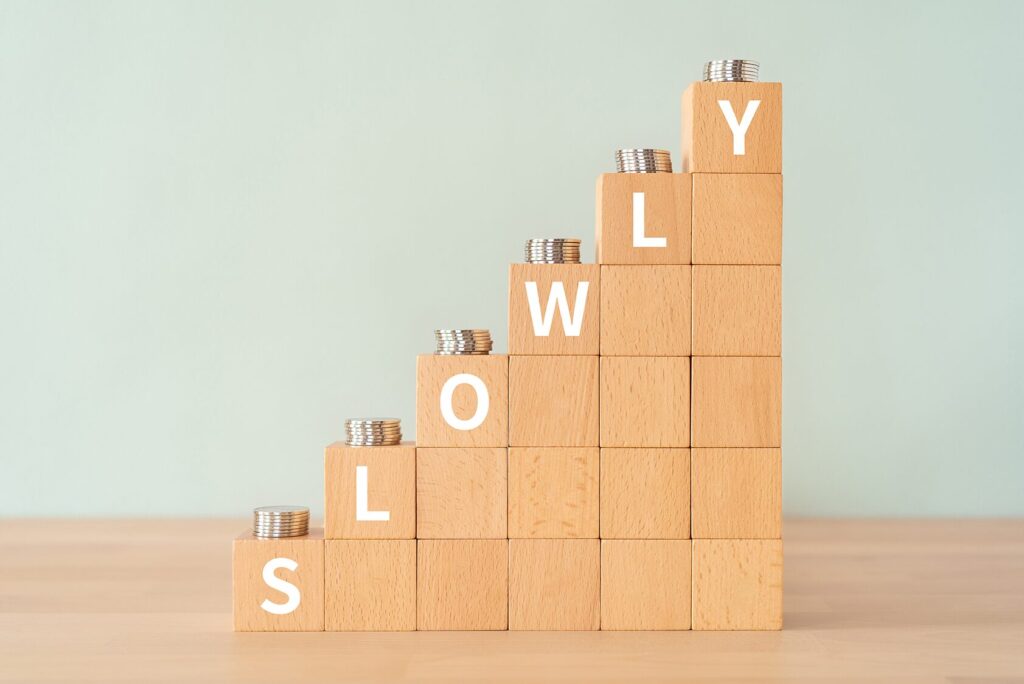
テーマ型投資信託は、販売側にとって「説明が簡単で売りやすく」、コストも高めで「利益率が高い」商品です。そして、短期で大きな利益を狙いたい短期志向の投資経験者が中心の市場となっています。
テーマが当たれば短期間で大きく儲かる可能性もありますが、外れるリスクも大きく、コストも高いため、シニアの皆様が目指す「長期にわたる安定的な資産形成」には向かない金融商品と言えます。
長期の資産運用では、「分散投資」と「低コスト」が鉄則です。
流行に惑わされず、手堅く資産を育てていくために、幅広い資産に分散投資する低コストの投資信託(例えば、世界の株式全体に投資するインデックスファンドなど)を選ぶことをおすすめします。
テーマ型投資信託について、理解を深めていただけたでしょうか? ご自身の大切な老後資金を守り、育てるために、流行やブームではない、しっかりとした知識に基づいた商品選びを心がけてくださいね。



コメント