最近、「年収103万円の壁」がニュースでよく取り上げられますが、実は年金の世界にも見過ごせない「壁」があるのをご存じでしょうか? それが、「年金211万円の壁」です。
この「211万円の壁」は、主に65歳以上のご夫婦が「住民税がかからない世帯」になれるかどうかの年金収入の目安なんです。
具体的に言うと、世帯主(多くの場合、夫)の年金収入が年間211万円以下、そして配偶者(多くの場合、妻)の年金収入が年間155万円以下であれば、ご夫婦全体が住民税非課税世帯になれる、という基準のことです。
「え、年金ってたくさんもらう方がいいんじゃないの?」そう思われるかもしれません。でも、実はこの「211万円の壁」には、ちょっとしたからくりがあるんです。
65歳からもらえるはずの年金を、あえて早めに(繰り上げて)もらい始めることで、年金額自体は減ります。しかし、その分、年金から自動的に引かれる社会保険料や税金が減り、結果として手元に残るお金(手取り額)が増える、というケースがあるんです。
「壁」の向こうとこちらで、こんなに違う!
この壁を境に、生活にかかるお金が大きく変わる可能性があります。住民税がゼロになるだけでなく、211万円以下になると、ご夫婦の年間の社会保険料が10万円近く安くなることもあります。さらに、医療費が高額になった際に戻ってくる「高額療養費制度」の自己負担上限額も低くなりますし、自治体によっては入院時の食事代が安くなるなどのサポートが受けられる場合もあるんです。
例えば、年間270万円(ひと月22万5千円)の年金を受け取れる方が、60歳から年金を繰り上げて受け取り始めると、年金が24%減額され、ちょうど非課税ラインの210万円になる、という計算もできます。
将来にわたって年金から引かれる保険料や税金を考えると、たとえ年金を年間60万円減らしてでも、「住民税非課税世帯」になることを選ぶのは、検討する価値がある、という考え方もあるわけです。
何より大きなポイントは「住民税」です。大都市圏にお住まいの65歳以上で、妻を扶養しているご主人の場合、年金収入が211万円以下であれば、住民税を払わずに済むことになります。
では、この「211万円の壁」を超えてしまうと、具体的にどのような負担が増えるのでしょうか?
なぜ「壁」と表現されるの? わずかな差が大きな負担増に!

「211万円の壁」を超えてしまうと、これだけの負担が増える!
「壁」という言葉が使われるのは、たった1円でもこの基準を超えてしまうと、皆さんの経済的負担が急に、そして大きく増えてしまうからです。
- 住民税が課税される:住民税(均等割と所得割)が新たに課税されます。特に、これまで住民税がかからなかった世帯は、均等割(年間約5,000円程度)も加わり、負担が増えます。
- 社会保険料が増える:
- 国民健康保険料の割引がなくなる、または少なくなる:住民税非課税世帯には、所得に応じた保険料の減免(割引)がありますが、課税世帯になると、この割引が適用されなくなり、保険料がグンと上がることがあります。
- 介護保険料の負担が増える:介護保険料も所得の段階に応じて決まります。住民税非課税世帯から外れると、保険料が引き上げられます。地域によっては、年間で数万円〜10万円以上も差が出ることもあります。
- 医療費や介護費用の自己負担額が増える:
- 高額療養費制度の自己負担限度額が高くなる:医療費が高額になった場合に、一定額を超えた分が戻ってくる高額療養費制度。住民税非課税世帯は自己負担の上限が低く設定されていますが、課税世帯になると上限額が高くなります。
- 高額介護サービス費の自己負担上限額が高くなる:介護サービス費についても同じで、非課税世帯は上限額が低く抑えられていますが、課税世帯になると上限額が上がります。
- 入院時の食事代や介護施設利用時の食費・居住費の負担が増える:住民税非課税世帯に適用される費用軽減の仕組みが受けられなくなります。
これらの負担増は、年金収入が少し増えただけでも発生するため、「たった1万円収入が増えただけで、年間で数万円〜10万円以上も負担が増える」ということが起こり得るのです。この急な負担の増加こそが、「壁」という言葉で表現される理由なんですね。
「211万円の壁」を考える上での大切な注意点
・地域によって基準が違うことも:今回お話しした「211万円」や「155万円」の基準は、主に「1級地」と呼ばれる大都市圏での目安です。お住まいの地域(級地)によって、非課税になる年金収入の限度額は異なる場合があります。正確な金額を知りたい場合は、お住まいの市区町村の住民税を担当する窓口で確認してください。
・夫婦の年金収入は合計額ではない:「世帯主の年金収入が211万円以下」と「配偶者の年金収入が155万円以下」というのは、それぞれ個別の基準です。夫婦の年金収入を合算した金額ではありませんので、混同しないようにしましょう。
・年金以外の収入があれば合算される:もし、年金収入以外に、お給料や不動産の家賃収入など、別の収入がある場合は、それらもすべて合わせた「所得金額」で判断されます。年金だけを切り離して考えることはできません。
この「211万円の壁」を意識することは、年金生活を送る上で、住民税や社会保険料、医療費・介護費用の負担を軽くし、手元に残るお金を最大限に増やすための、とても重要なポイントになります。
住民税非課税世帯になると、こんなメリットも!
住民税非課税世帯になると、金銭的な負担が減るだけでなく、実は他にもいろいろな良いことがあります。
自治体のサービスや給付金の対象に:国や地方自治体から、低所得者向けの特別な給付金などが支給されることがあります。
教育費の減免・無償化:もしお子さんやお孫さんがいる場合、大学などの授業料や入学金が免除・減額されたり、返済不要の奨学金がもらえたりすることがあります。また、0歳から2歳のお子さんの保育料が無償になります。
各種割引や補助:予防接種の費用が補助されたり、バスや電車などの交通費が割引になったり、健康診断が無料になったりと、自治体独自のサービスが受けられる場合があります。
NHK受信料の免除:一定の条件を満たせば、NHKの受信料が免除されます。
年金繰り上げ受給には、大きな「危険」も潜んでいます!

住民税非課税世帯になるメリットは確かに魅力的です。しかし、年金を早めに受け取る「繰り上げ受給」を選ぶことには、見逃せない大きなデメリットも存在します。ここが、まさに今回のテーマである「危険」な部分です。
生涯にわたる年金額の減額:一度繰り上げ受給を選んでしまうと、年金が減る割合は、生きている限りずっと続きます。もし長生きした場合、生涯でもらえる年金の合計額は、結果的に大きく減ってしまう可能性があります。一度決めたら、後から取り消すことはできません。
障害年金や遺族年金に影響が出る可能性:繰り上げ受給をすると、もしもの時に受け取れる障害基礎年金や、ご主人が亡くなった際に妻がもらえる寡婦年金などが、受け取れなくなったり、支給が止まったりする場合があります。
国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなる:年金額を増やすために、国民年金に任意で加入したり、過去の保険料をまとめて払ったりする選択肢が制限されてしまいます。
配偶者加給年金への影響:もし65歳未満の配偶者がいる場合、年金に上乗せされる「加給年金」が、もらえない期間が出てくることがあります。
雇用保険の基本手当(失業保険)との調整:65歳になるまでの間に雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受け取る場合、年金が一時的に支給停止となることがあります。
参考記事:繰下げ受給がベストチョイス: 公的年金の賢い選択方法を解説

今後、住民税非課税の基準が厳しくなる可能性も…

住民税非課税の基準は、国の経済状況や政策によって変わる可能性があります。今後、住民税を払う人を増やそうという動きが出てこないとは限りません。
また、最近は物価が上がり続けるインフレ傾向にあります。もし今、年金を繰り上げて211万円以内に収めていても、毎年の年金改定によって、すぐに211万円を超えてしまう可能性もゼロではありません。
そして、何よりも怖いのが、一度年金の繰り上げ受給を選ぶと、後から元に戻すことができないという点です。もし、将来の改定で住民税が課税されることになり、税金が増えるにもかかわらず、年金は減額されたままでは、それ以降の老後の生活はとても厳しいものになってしまいます。これはまさに「後悔しかない」状況になりかねません。
このような状況では、私たちが一番心配する「長生きリスク」(長生きすることでお金が足りなくなるリスク)に対応できなくなってしまうんです。
まとめ
年金繰り上げは慎重に、そして専門家と相談を!
年金を早めにもらう「繰り上げ受給」は、一時的に年金収入を減らすことで住民税非課税世帯となり、税金が安くなるなどのメリットがあるように見えます。しかし、その裏には、生涯にわたる年金額の減額や、他の大切な年金制度への影響といった、非常に大きなデメリットが潜んでいます。
ご自身の健康状態、今ある貯蓄の状況、そしてこれから先の生活をどうしたいのか、といったことを総合的にじっくり考える必要があります。そして、年金事務所や税務署、あるいはファイナンシャルプランナーといったお金の専門家に相談して、ご自身にとって一番良い選択肢は何かを、くれぐれも慎重に判断することをおすすめします。
いかがでしたでしょうか? この記事が、皆さんの年金生活を考える上で、少しでもお役に立てれば幸いです。もし気になる点や、さらに詳しく知りたいことがあれば、お気軽にご質問ください。
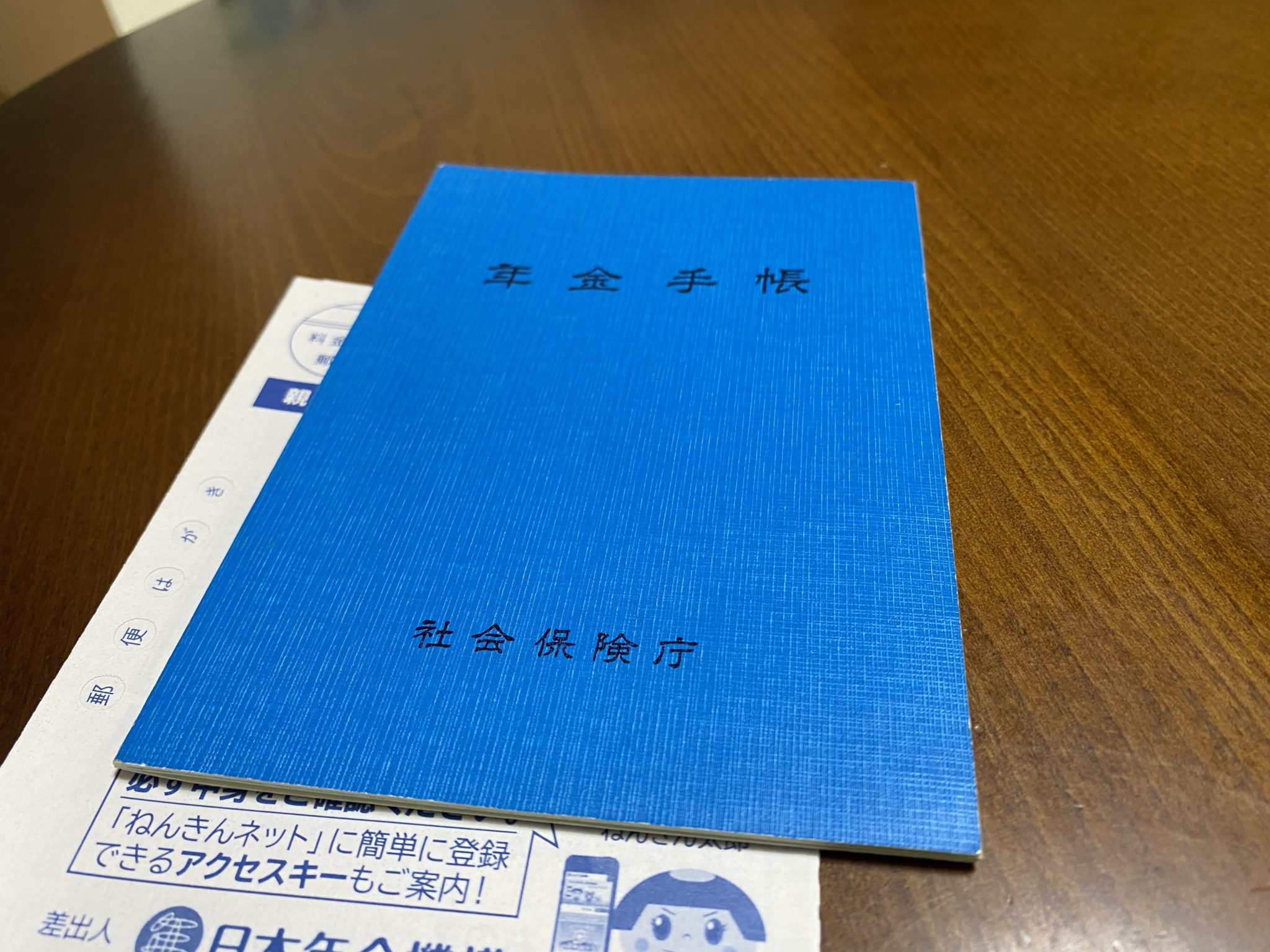

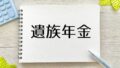
コメント