「最近、高い利回りが期待できる『劣後債(れつごさい)』という債券が個人向けにも売られているらしい」
そんな話を耳にして、「手元の資金を少しでも増やしたい」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。特に、インターネットの証券会社などでは、10万円程度から買えるものも登場し、積極的におすすめされています。
しかし、結論から申し上げると、一般の個人投資家、特にこれから投資を始めようと考えているシニアの方々にとって、この「劣後債」という商品は、あまりおすすめできません。
なぜなら、この債券は、一見すると普通の債券や預金よりも魅力的に見えますが、実は非常に複雑で、「まさかこんなことになるとは」という落とし穴が隠れているからです。
ここでは、あなたが大切なお金を失わないために、「劣後債を買ってはいけない3つの理由」を、専門用語を使わずにわかりやすく解説します。
そもそも「劣後債」って、普通の債券とどこが違うの?
「劣後債」という名前を聞き慣れない方も多いでしょう。
普通の債券は、企業や国がお金を借りるために発行する「借用書」のようなものです。満期になれば、借りたお金(元本)が全額、利息と一緒に戻ってくるのが基本です。
これに対して「劣後債」は、文字通り「返してもらう順番が劣る(おくれる)債券」という意味です。
返済の順番が遅い代わりに、利息が高い!
企業がもし倒産するなどして、借金を返すのが難しくなった場合、お金を返してもらう人たち(債権者)には、あらかじめ決められた「順番」があります。
- まず、銀行などの普通の借金や、普通の債券を持っている人に返済されます。
- その次に、この「劣後債」を持っている人に返済されます。
- 最後に、株主などに残ったものが渡されます。
つまり、劣後債は、「普通の債券の人たちより後に回されてもいいですよ」という条件で、企業にお金を貸していることになります。
普通の債券よりもお金が戻ってこないリスク(危険性)が高い分、発行する企業は「リスクを取ってくれてありがとう」という意味で、普通の債券よりも高い利息(金利)を付けて、私たちに買ってもらおうとしているのです。
過去に劣後債を発行した代表的な企業例(高利回り順)
実際に劣後債を発行した代表的な企業には、楽天証券では、株式会社みずほ銀行、日本生命、SBI証券では、三菱UFJフィナンシャル・グループなどが挙げられる。
ただし、これらの情報は過去に販売された時点のデータであり、現在購入できるか、また同じ条件であるかは保証されません。あくまで「このような商品があった」という例としてご覧ください。
| 発行企業名 | 金利/年(税引前) | 債券格付 | 期間(償還まで) |
| 日本生命 | 6.25% | A | (不明) |
| 株式会社みずほ銀行 | 4.84% | A | 約5年 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.96% | A- | 約4.4年 |
【要注意!】買ってはいけない3つの落とし穴

高い利息に惹かれてしまいがちですが、この劣後債には一般の投資家にはわかりにくい、大きなリスクが潜んでいます。
その1: 会社が危なくなると、大切なお金が全額戻らない!
これが劣後債の最大のリスクです。
普通の債券や銀行預金であれば、預け先が倒産しない限り、満期には元本(預けたお金)が全額戻ってきます。
しかし、劣後債は「返済の順番が後回し」です。もし発行した企業が倒産したり、経営が非常に苦しくなったりした場合、先に返済を受ける人たち(普通の債券を持っている人など)にお金を返し終わると、劣後債を持っている人には、返すお金が残らない可能性があります。
つまり、預けたお金が一部、あるいは全額、戻ってこないかもしれないという、非常に大きな危険性があるのです。
その2: 想定していた高い利息(リターン)が、途中で得られなくなる!
劣後債には、多くの場合、企業が「満期より前に、勝手に返済していいですよ」という約束(専門用語では「期限前償還条項」といいます)がついています。
企業は、この債券を発行する際、「〇年くらいお金を借りておきたいな」という目的を持って発行します。そして、借りておきたい期間が短くなると、「もう借りておくメリットが薄れたから」と判断し、満期を待たずに、企業側の都合で私たちに元本を返してきてしまうことがあるのです。
例えば、10年間の予定で高い利息が付く劣後債を買ったとしても、5年で返済されてしまったらどうなるでしょうか?
「お金が戻ってきた」と聞くと安心しますが、裏を返せば、残りの5年間でもらえたはずの高い利息を、一切受け取れなくなるということです。せっかく高い利回りを期待して投資したのに、そのメリットが途中で失われてしまう可能性があるのです。
その3: 証券会社の「隠れた手数料稼ぎ」の餌になってしまう!
私たちが株式や投資信託を買うときには、「手数料」がいくらと、はっきり決められています。
しかし、債券を証券会社から買う場合、「手数料はかかりませんよ」と言われることがあります。
これは、実は大きな落とし穴です。
証券会社は、この債券を企業などから仕入れた時の価格に、自分たちの利益(手数料のようなもの)を上乗せして、私たちに売っています。そして、この上乗せする金額は、証券会社が自由に決められるため、私たち購入者には「この会社はどれだけ儲けているのか」が一切わかりません。
特に劣後債のような複雑で、高い利息で誘われる商品は、一般の投資家にはリスクの大きさが判断しにくいため、証券会社の「手数料稼ぎ」のターゲットになりやすいのです。
もしあなたが金融機関の窓口などで「これは良い商品ですよ」と熱心におすすめされたとしても、その商品の裏に「販売会社(証券会社など)の大きな利益」が隠れていないか、慎重に考える必要があります。
まとめ:「わからないもの」には手を出さないのが賢明です
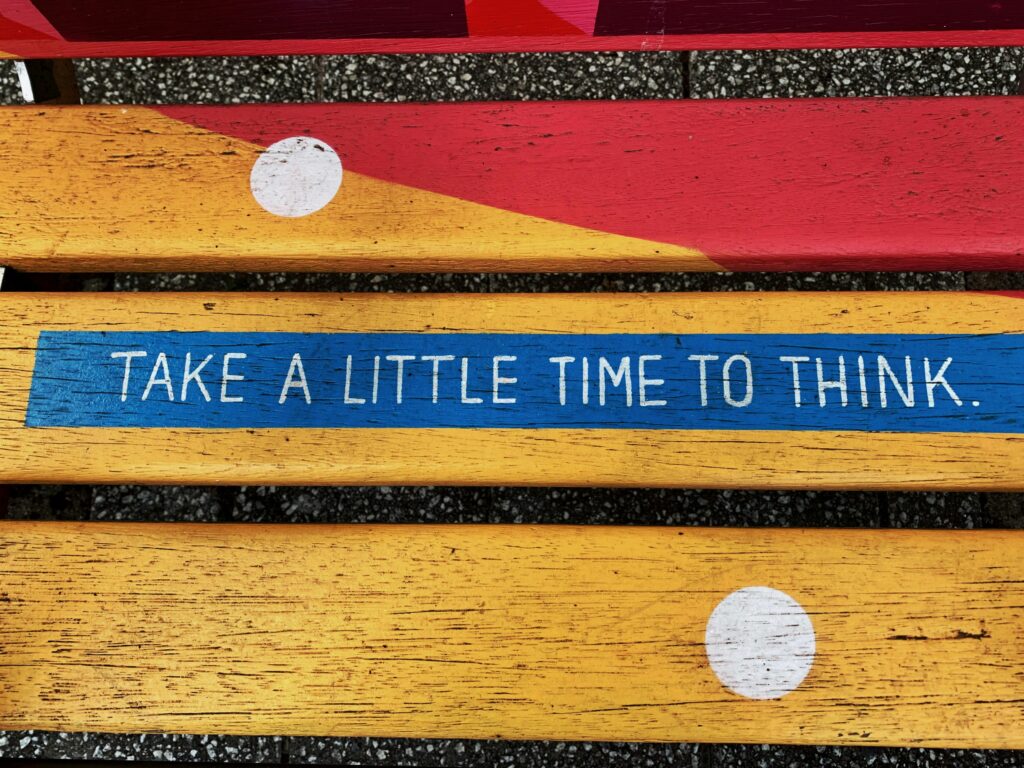
一般的に、債券への投資は、株や投資信託などに比べてリスクが低い分散投資の方法として有効です。
しかし、この「劣後債」のように、
- 返済の順番が後回しという複雑な仕組み
- 外国の通貨建てであることによる、円高・円安による影響(為替リスク)
- 企業側の都合で高い利息の期間が短くなる可能性
など、一般の個人投資家がその危険性を自分で判断し、把握することが非常に難しい商品です。
もちろん、仕組みを完璧に理解し、リスクを十分承知の上で投資をするのであれば問題ありません。しかし、「高い利息」という魅力だけで、よくわからない複雑な金融商品に大切なお金を出してしまうのは、あなたの財産を守る上で賢明な選択とは言えません。
「知らないことは、手を出さない」
この原則こそが、シニア世代の穏やかな資産運用にとって、最も大切な心得なのです。
いかがでしたでしょうか。
シニアの皆さまの資産運用の一助となれば幸いです。また何かご質問がありましたら、いつでもお声がけください。



コメント