皆さん、こんにちは!シニアの皆さんにとって、セカンドライフを安心して送るためには、やはり健康が一番ですよね。そして、健康な毎日を支える上で欠かせないのが健康保険です。
会社を退職した後、健康保険はどうなるの?と不安に思っている方もいらっしゃるかもしれません。今回は、そんな皆さんの不安を解消し、セカンドライフを賢く過ごすための選択肢の一つである「特例退職被保険者制度」について、できるだけわかりやすくご説明したいと思います。
この制度が紹介されることが少ないのは、実施している保険組合が、とても少ないためです。
少し古いですが、2014年に、厚労省が調べたところ、健康保険組合は約1,400ありますが、そのうち「特例退職者被保険制度」があるのは61組合しかない極めて稀な制度です。
しかし、もし利用できるのであれば大きなメリットがある制度なのです。
退職後の健康保険、どうなるの?
会社を退職すると、これまで会社で加入していた健康保険(多くの場合は「被用者保険」と呼ばれる健康保険組合や協会けんぽなど)からは原則として外れることになります。では、退職後はどのような健康保険の選択肢があるのでしょうか?
主な選択肢は以下の3つです。
- 国民健康保険に加入する:お住まいの市区町村が運営する健康保険です。
- ご家族の健康保険の扶養に入る:配偶者や子どもの健康保険の扶養に入れる条件を満たしている場合です。
- 任意継続被保険者制度を利用する:退職した会社の健康保険に、引き続き最大2年間加入できる制度です。
これらに加えて、今回ご紹介する特例退職被保険者制度という選択肢もあるんです。
特例退職被保険者制度って、どんな制度?
特例退職被保険者制度は、簡単に言うと「会社を退職しても、特定の条件を満たせば、これまで加入していた健康保険組合に引き続き加入できる制度」です。
「え、任意継続と何が違うの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
任意継続は、退職した会社の健康保険に最長2年間加入できますが、この特例退職被保険者制度は、条件を満たせば2年を過ぎても継続して加入できる点が大きな違いです。
つまり、定年後も会社員時代と同じ健康保険に、長く加入し続けられる可能性がある、という点がこの制度の大きな魅力と言えるでしょう。
ただし、この制度はすべての健康保険組合にあるわけではありません。特定の健康保険組合が独自に設けている制度なので、ご自身が加入していた健康保険組合がこの制度を導入しているかどうかの確認がまず必要になります。
どんな人が利用できるの?加入するための条件
特例退職被保険者制度を利用するには、いくつか条件があります。主な条件は以下の通りです。
- 一定期間、その健康保険組合の健康保険に入っていたこと:
- たとえば、「退職前20年以上、この健康保険組合に加入していたこと」という条件や、「40歳以降で10年〜15年以上加入していたこと(健康保険組合によって年数は異なります)」といった条件がよく見られます。
- 退職時の年齢が一定以上であること:
- 多くの場合は、定年退職などを想定して「〇歳以上で退職したこと」といった条件があります。
- 年金をもらう権利があること(または将来もらえる見込みがあること):
- この制度は、主に年金生活に入った方を対象としているため、年金受給との関連が深いのが特徴です。例えば、年金の支給がまだ始まっていない場合、「特例退職被保険者制度」には加入できず、一時的に「任意継続」や「国民健康保険」に加入する必要があるケースもあります。特に、男性で1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた方は、老齢厚生年金の受給開始年齢が65歳からとなるため、それまでは注意が必要です。
- 他の健康保険に加入していないこと:
- 国民健康保険など、他の健康保険にすでに加入している場合は、この制度は利用できません。
- 健康保険組合が定めるその他の条件:
- 上記以外にも、健康保険組合ごとに細かな条件が設けられている場合があります。
これらの条件は、皆さんの健康保険組合によって異なります。ご自身の健康保険組合のルールをしっかり確認することが大切です。
特例退職被保険者制度の大きなメリットとは?
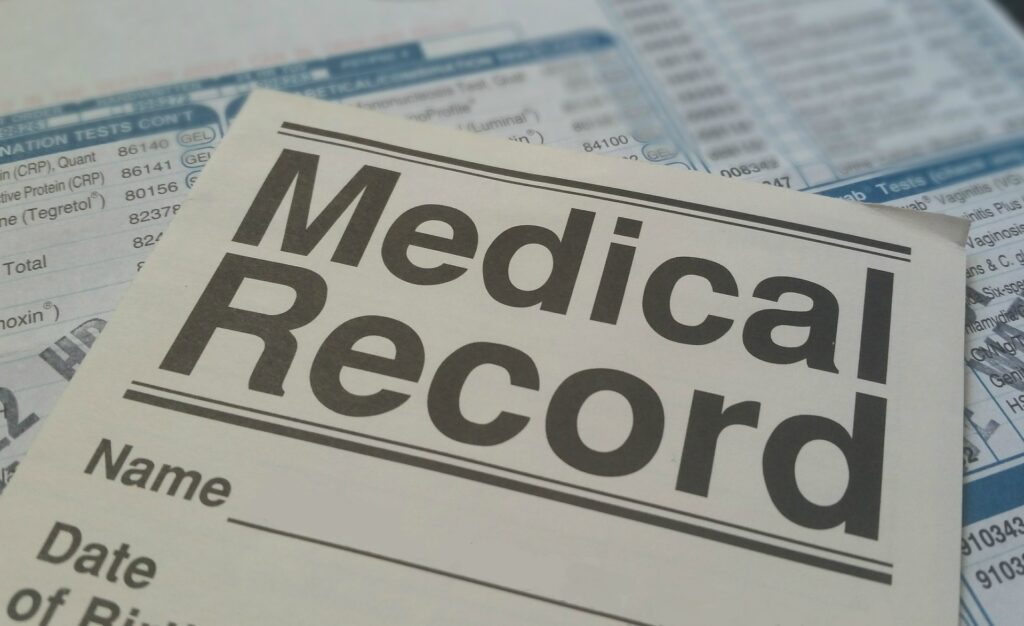
この制度には、次の3つの大きなメリットがあります。
1.現役社員と同じような医療サービスや特典を受けられる可能性がある:
- 健康保険組合によっては、通常の医療費の補助に加えて、人間ドックの費用が割引になったり、無料になったり、保養所などを安く利用できたりするサービスを用意している場合があります。これは、国民健康保険にはない大きな魅力ですね。
- また、高額な医療費がかかっても、健康保険組合独自のルール(付加給付制度)によって、自己負担額が2万円から3万円程度に抑えられる場合もあります。これは本当に心強いですよね。
2.扶養家族も一緒に入れる可能性があり、保険料がお得になることも:
- 一定の収入要件を満たせば、配偶者やお子さんなど、皆さんの扶養家族も引き続き健康保険に加入できます。家族分の保険料を個別に払う必要がないため、家計全体の保険料負担を抑えられる可能性があります。
3.「74歳」まで長く利用できる期間の長さ:
- 任意継続制度が最長2年間なのに対し、この特例退職被保険者制度は、後期高齢者医療制度が始まる75歳になるまで(つまり74歳まで)、長く利用できる点が最大のメリットと言えるでしょう。長期的に安心して健康保険に加入できるのは、シニア世代にとって非常に重要なポイントです。
注意点!この制度はごく一部の健康保険組合だけ
残念ながら、この特例退職被保険者制度は、すべての健康保険組合にあるわけではありません。現在、この制度を導入しているのはごく限られた「特定健康保険組合」だけです。
また、加入できる条件も、働いていた期間が長いことなど、厳しく設定されていることが多いです。
「うちの健康保険組合はどうなんだろう?」と思ったら、まずは、お勤めだった会社の健康保険組合のホームページを確認するか、直接問い合わせてみましょう。もし、制度がある組合なら、皆さんのシニアライフにとって大きな助けになるはずです。
この制度の存在を知らないままだと、利用できるチャンスを逃してしまうかもしれません。ぜひ、ご自身の健康保険組合の情報を確認してみてください。(*現在は、特定健康保険組合の認可が取消されていることもある可能性もございますのでご注意ください。)

出典:平成26年11月7日 第84回社会保障審議会医療保険部会
特例退職被保険者制度の保険料はいくら?
特例退職被保険者制度の保険料は、皆さんの健康保険組合によって計算方法が異なります。一般的には、会社を退職した時の給料(正確には「標準報酬月額」という健康保険料の計算基準になる金額)や、前年の所得などをもとに計算されます。
会社員時代は、保険料の半分を会社が負担してくれていましたが、特例退職被保険者になると、原則として全額自己負担になります。そのため、「保険料が会社員時代より高くなった」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
具体的な保険料を知るためには、ご自身が加入していた健康保険組合に直接問い合わせるのが一番確実です。ご自身の年金収入や家族構成などによって、国民健康保険や他の選択肢と比べてどちらがお得になるかは変わってくるので、しっかり比較検討することが大切です。
国民健康保険、任意継続との比較
ここで、退職後の健康保険の選択肢としてよく比較される「国民健康保険」と「任意継続被保険者制度」、そして「特例退職被保険者制度」を簡単に比較してみましょう。
| 制度名 | 加入できる期間 | 保険料の計算方法 | 独自の特典(付加給付など) | 扶養家族の加入 |
| 特例退職被保険者 | 条件を満たせば74歳まで長期 | 組合によって異なる(退職時の給料や前年所得など) | ある可能性あり | 加入可能 |
| 国民健康保険 | 期間の定めなし | 前年所得や世帯人数、市区町村によって異なる | 基本的になし | なし(世帯全体で加入) |
| 任意継続被保険者 | 最長2年間 | 退職時の給料(または上限額)を元に計算 | 基本的になし | 加入可能 |
これはあくまで一般的な比較です。皆さんの具体的な状況や、加入していた健康保険組合のルールによって内容は大きく変わりますので、ご注意ください。
どうすれば特例退職被保険者制度に加入できるの?手続きの流れ
もし特例退職被保険者制度の利用を検討するなら、次のような流れで進めることになります。
- ご自身が加入していた健康保険組合に問い合わせる:
- まず、皆さんの健康保険組合が特例退職被保険者制度を導入しているかを確認しましょう。
- 導入している場合、加入するための条件や保険料の計算方法、手続きに必要な書類などを詳しく聞いてください。健康保険組合のホームページなどで情報が公開されている場合もあります。
- 他の選択肢とじっくり比較する:
- 特例退職被保険者制度の保険料やメリット・デメリットが分かったら、国民健康保険やご家族の扶養に入る場合、任意継続のメリット・デメリットと比較検討しましょう。
- ご自身の年金収入、貯蓄、今後の生活設計などを踏まえて、どの選択肢が一番皆さんに合っているかをじっくり考えてみてください。
- 必要書類を準備して、申請する:
- 加入を決めたら、健康保険組合の指示に従って必要な書類(退職証明書、年金証書、住民票など)を準備し、期日までに申請手続きを行います。書類に不備がないか、よく確認しながら進めましょう。
まとめ:セカンドライフの健康保険、賢く選んで安心を!

特例退職被保険者制度は、誰もが利用できるわけではない、少し特殊な制度です。でも、もし皆さんが条件に合うなら、セカンドライフの健康保険として非常に有力な選択肢となり得ます。
特に、
- これまで長く会社員として特定の健康保険組合に加入していた方
- 定年退職後も安心できる医療サービスを受け続けたい方
- 保険料の負担を少しでも抑えたいと考えている方
にとっては、ぜひ検討してみてほしい制度です。
大切なのは、退職前にご自身の健康保険組合に問い合わせて、制度の有無や詳細な条件をしっかりと確認することです。そして、国民健康保険や任意継続など、他の選択肢ともじっくり比較検討し、ご自身のライフスタイルや経済状況に最も合った健康保険を選ぶことが、充実したセカンドライフを送るための第一歩となるでしょう。
わからないことや不安なことがあれば、一人で悩まず、健康保険組合の窓口や年金事務所、お住まいの市区町村の窓口などに相談してみてくださいね。
皆さんのセカンドライフが、健康で豊かなものになりますように!


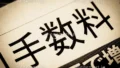
コメント